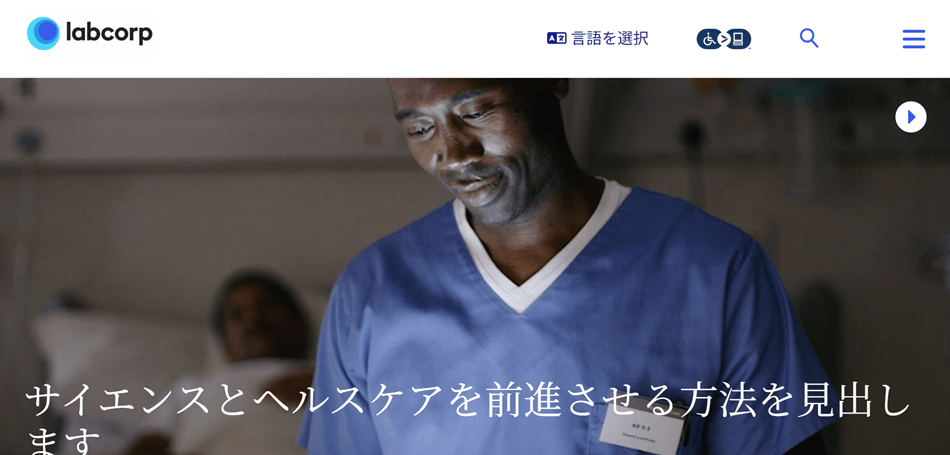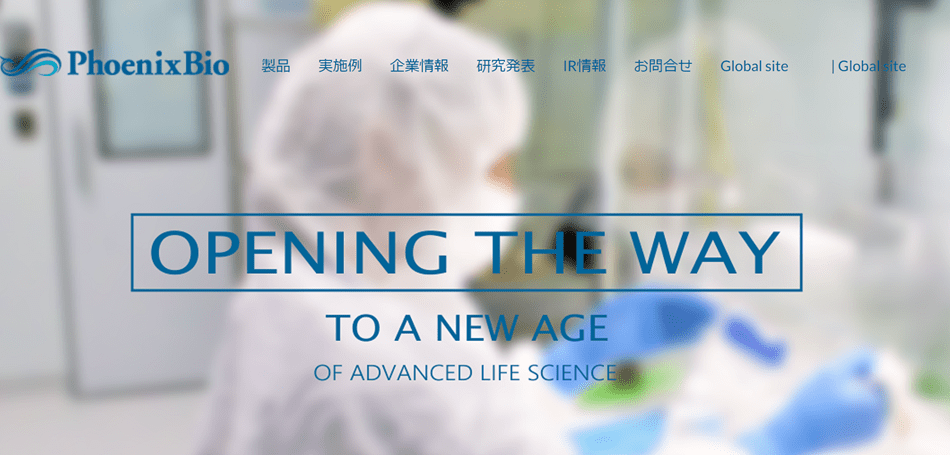薬物安全性試験センター
薬物安全性試験センターは、40年以上にわたり、質の高い非臨床試験サービスを提供している企業です。ここでは、薬物安全性試験センターの非臨床試験の特徴や病態モデル一例、事例などを詳しく紹介します。受託会社を選ぶ際の参考にしてください。
薬物安全性試験センターの非臨床試験の受託サービスの特徴
迅速な対応力
要望に応じた迅速かつ丁寧な対応を心掛けています。特に感作性試験、マニュアルパッチクランプ試験のデータ提出はスピーディです。初めて試験を依頼する方でも安心して利用できるサポートプランを用意しています。
提案力が高い
「どのような評価項目が必要か?」「想定外の結果を受け次のステップは? 」といった委託前後に生じる様々な疑問に対して、丁寧に応える方針です。開発品の特徴や希望に応じて、ベストなソリューションを提案できます。
リーズナブルな価格
品質と同様に価格も重要だと考えています。品質を落とさないことを大前提として、コストカットを常に模索することで、高品質のデータを納得の価格で提供するのがモットーです。価格・納期・品質のバランスを重視したコストパフォーマンスの高いサービスを実現しています。
薬物安全性試験センターが保有する病態モデル一例
病気を治す薬を開発するには、治したい病気を発症した実験動物に対して新薬をテストし、効果のある成分を見つけ出してから臨床試験に臨むのが重要です。
しかし、治したい病気を発症する動物モデルが存在するとは限りません。もしまだ世に無い場合は、場合によっては新規開発してもらう必要もあります。ここでは、同社が保有している動物の病態モデルについて一例をご紹介しています。
ウサギキモトリプシン誘発高眼圧モデル試験
眼科薬理試験のなかでも、緑内障や網膜関連の試験として使用されたウサギモデルです。高眼圧状態が継続的に維持できる慢性緑内障モデルとして、眼圧下降薬や緑内障視神経症治療薬、網膜症治療薬の評価に適用されます。
イヌ乾燥性ドライアイモデル試験
眼科薬理試験のなかでも、角膜疾患モデルとして使用された病態モデルです。イヌの角膜に一定量の風を強制的にあて、角膜を乾燥させることで乾燥性ドライアイを再現します。角膜上皮障害性ドライアイ治療薬に適用されます。
ラット水圧負荷虚血再灌流網膜症モデル試験
眼科薬理試験のなかでも、緑内障や網膜関連の試験として使用された病態モデルです。前房内に生理食塩液を注入し、100mHg程度の高眼圧状態を一過性に負荷することで網膜症を再現します。網膜症治療薬の評価に適用されます。
薬物安全性試験センターの非臨床試験事例
公式サイトに事例が記載されていませんでした。
薬物安全性試験センターの企業情報
40年以上の長きにわたって、医薬品や医薬部外品、動物用医薬品など良質な非臨床試験サービスを提供し続けている企業です。
| 会社所在地 |
東京都新宿区高田馬場1-31-8 |
| 電話番号 |
0493-54-3239 |
| 公式サイト |
https://www.dstc.jp/ |