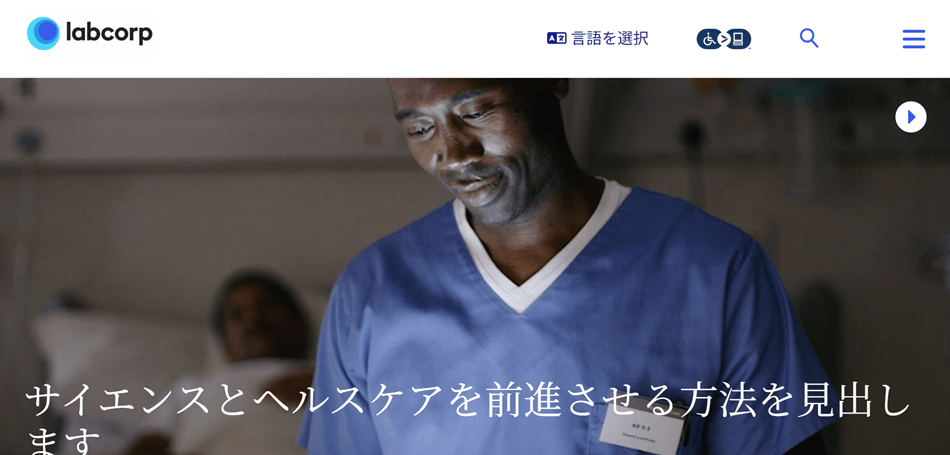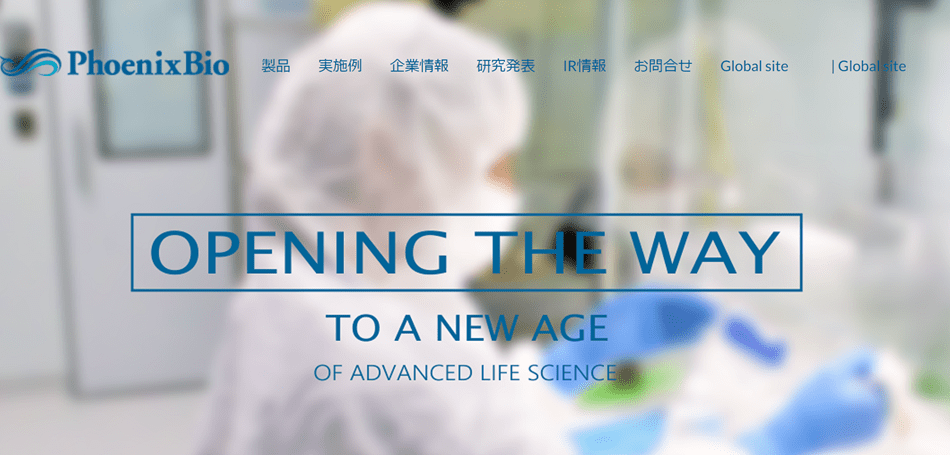網膜神経疾患の創薬
網膜神経疾患は視覚障害を引き起こす深刻な病態です。特に、緑内障や網膜色素変性などの疾患は進行性であり、効果的な治療法が限られています。これらの疾患に対する創薬は、視覚機能を回復させるために極めて重要です。過去の事例として、ヒトiPS細胞を用いた視神経細胞の作製技術が注目されています。この技術により、網膜神経疾患の治療薬開発が進展しました。
以下では、網膜神経疾患治療のための具体的な事例を紹介し、それぞれの非臨床試験の内容を解説します。
国立成育医療研究センターの開発事例
国立成育医療研究センターでは、ヒトiPS細胞から視神経細胞(網膜神経節細胞)を作製することに成功しました。これにより、重篤な視覚障害を引き起こす視神経疾患の原因や病態の解明、診断・治療の研究が大きく進展しました。さらに、薬物の効果を判定する技術も開発され、視神経疾患に対する新たな治療薬の開発が可能となりました。
非臨床試験の内容
国立成育医療研究センターでは、ヒトiPS細胞およびマウスのiPS細胞やES細胞から視神経細胞を作製し、視神経を障害する疾患の病態解明や診断技術の研究、治療のための創薬、視神経の移植や再生医療などの臨床研究、視神経の発生、神経線維成長における経路探索のメカニズム、視覚成立の分子メカニズムなど、網膜神経疾患の治療に大きく貢献します。
日本薬理学会の開発事例
日本薬理学会では、網膜変性疾患や視覚情報伝達をテーマに、メカニズムや病態の解明、新規治療法の研究が行われています。例えば、緑内障や網膜色素変性におけるmicroRNAの役割を解明し、これをターゲットとした神経保護薬の開発が進められています。また、ヒトiPS細胞由来視細胞シートの移植による網膜色素変性治療の臨床試験も始まっています。
非臨床試験の内容
日本薬理学会では、網膜色素変性モデルマウスを用いて、ヒトiPS細胞由来視細胞シートの移植による新規治療法の基礎的検討が行われています。これにより、視機能障害に対する治療戦略の可能性が示されました。
まとめ
網膜神経疾患は、有効な治療法が限られているため、創薬の重要性が高まっています。国立成育医療研究センターと日本薬理学会の事例からも分かるように、革新的な技術と研究が進められています。これらの取り組みにより、視神経疾患に対する新たな治療薬の開発が期待されています。製薬会社や研究機関が提供する薬効評価試験サービスを活用し、さらなる研究と開発が進むことを期待しています。