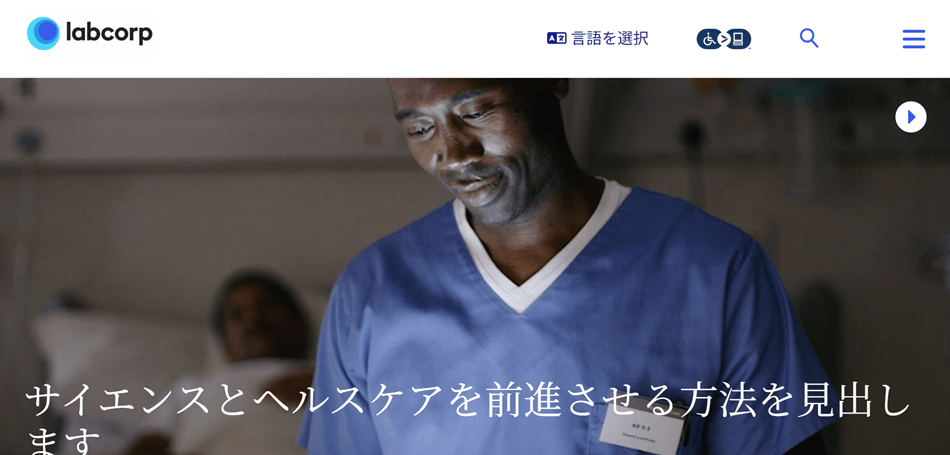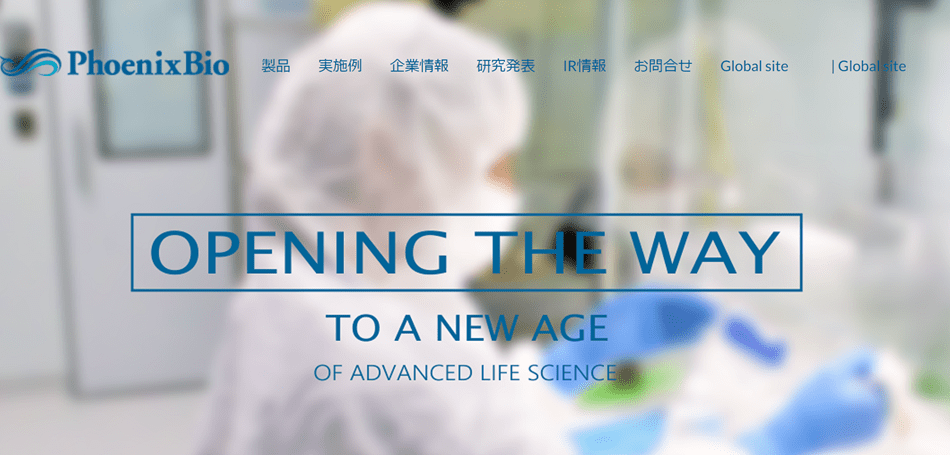神経変性疾患の創薬
神経変性疾患は、脳や神経の細胞が徐々に機能を失うことで進行する病気で、アルツハイマー病やパーキンソン病が代表例です。創薬においては、多くの企業が画期的な治療法を模索し、試験を繰り返してきました。以下の記事では過去の創薬事例を通じて、神経変性疾患の新薬開発がどのように進められてきたのかを紹介していきます。
エーザイ株式会社の開発事例
エーザイは、ドイツ神経変性疾患センター(DZNE)と共同で、アルツハイマー病をはじめとする神経変性疾患の新規治療候補品を開発しています。この共同研究は、神経・グリア細胞における免疫制御を活用し、新しい治療法の創出を目指しています。DZNEは、ドイツ国内の10拠点で構成される神経変性疾患の予防、診断、治療に関する学際的研究を推進する公的機関です。エーザイの豊富な創薬経験とDZNEの専門知識を組み合わせることで、新規治療候補品の創出が加速しています。
非臨床試験の内容
神経変性疾患領域での有効的な治療法の製作において豊富な実績のあるエーザイと、神経変性疾患の基礎および臨床研究の専門知識を有するDZNEが、基礎研究と臨床研究の連携により、疾患プロセス研究における知見と技術的専門知識に貢献しています。
小野薬品工業株式会社の開発事例
小野薬品工業は、スイスのNeurimmune AG社と提携し、神経変性疾患に対する抗体医薬品の開発を進めています。Neurimmune社のRTMTM技術を活用し、新たな創薬標的に対するヒトモノクローナル抗体を創製しています。この提携により、アルツハイマー病、パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症(ALS)など、複数の神経変性疾患に対する治療薬の開発が加速しています。
非臨床試験の内容
小野薬品工業とNeurimmuneの提携では、ALS(筋萎縮性側索硬化症)に対する抗miSOD1抗体、ATTR心筋症に対する抗ATTR抗体NI006を発見し、これらの非臨床試験が行われています。
まとめ
アルツハイマー病やパーキンソン病が代表例の神経変性疾患の創薬において、多くの企業が画期的な治療法を模索し、試験を繰り返してきました。
神経変性疾患の創薬は、エーザイや小野薬品工業などの企業が積極的に取り組んでいる分野です。両社の事例から、非臨床試験の重要性と具体的な内容が明らかになり、新たな治療法の開発が進行することで、今後もさらなる研究と試験が期待されます。