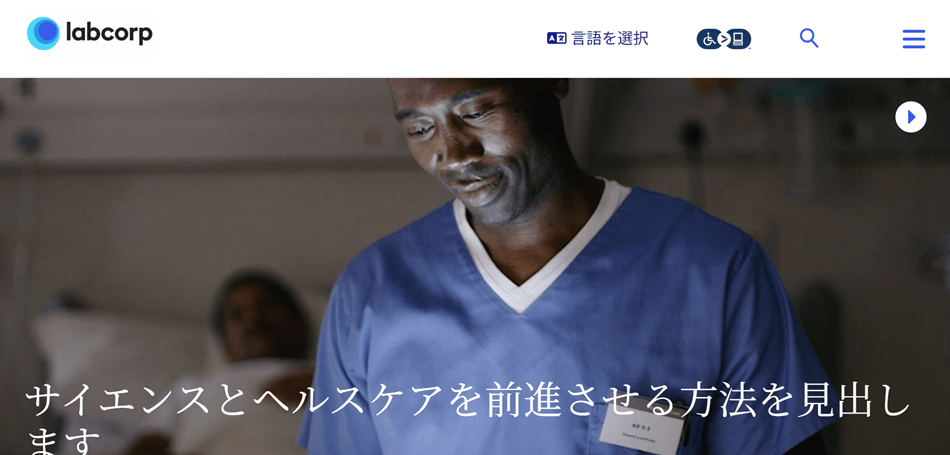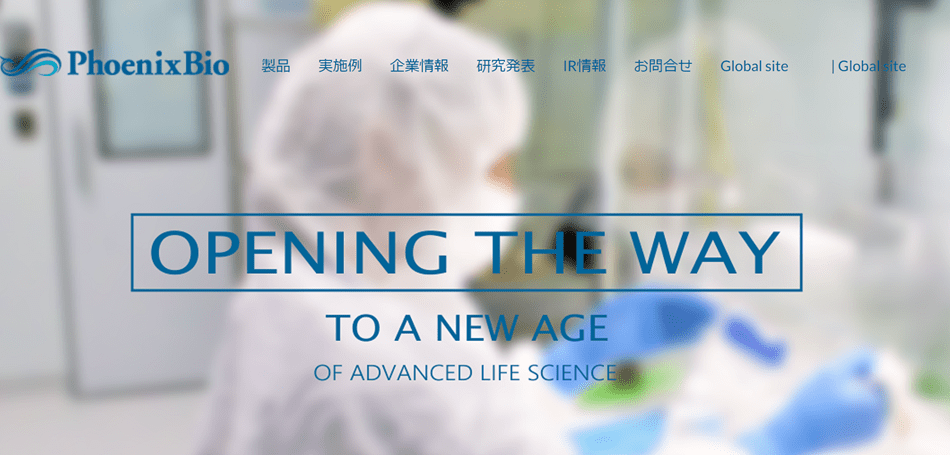臓器線維化の治療を目指す創薬
臓器線維化は、肝臓や肺、腎臓などの主要な臓器で起こる深刻な病態です。この症状は、臓器の機能を損ない、患者の生活の質を大きく低下させ、有効な治療薬のない難病とされています。特に、線維化が進行すると元の機能を取り戻すことが難しくなるため、早期の治療が重要です。
臓器線維化の治療を目指す創薬は、こうした背景から注目を集めています。以下では、臓器線維化治療のための創薬事例を紹介し、それぞれどのような非臨床試験が使われたかを紹介します。
SMCラボラトリーズ株式会社の事例
SMCラボラトリーズでは、線維化に着目した医薬品開発を行っており、炎症や線維化の病態を対象とした複数の臓器での薬効評価試験を実施しています。最近の研究では、AIを用いて特定されたTRAF2- and NCK-interacting kinase (TNIK) を抗線維化のターゲット(TNIK)に対する治療薬が、肺、皮膚、腎臓の線維化モデル動物で非臨床試験を実施しました。この結果は、Nature Biotechnology誌にも掲載され、注目されています。
非臨床試験の内容
この治療薬の非臨床試験では、マウスモデルを使用しました。特に、肺、皮膚、腎臓の線維化を再現したモデル動物で、治療薬の効果を評価しました。これにより、複数の臓器に対する同一化合物が評価され、特に有望な疾患に対する開発を進めた企業もいます。
日東電工株式会社の事例
日東電工は、特発性肺線維症を対象とした治療薬「ND-L02-s0201」を開発しています。この薬は、HSP47 siRNA製剤であり、コラーゲン生成を抑制することで線維症を治療します。国際共同第2相臨床試験では、安全性と忍容性に優れた結果が得られましたが、期待していた有効性を明確に示すことはできませんでした。
非臨床試験の内容
「ND-L02-s0201」の非臨床試験では、肝線維症モデルを使用して評価が行われました。非アルコール性脂肪肝炎(NASH)由来の肝線維症モデルでも試験が行われましたが、こちらの試験は中止となりました。
まとめ
臓器線維化は有効な治療薬のない病気として、日本では難病指定されています。SMCラボラトリーズと日東電工の事例からも分かるように、複数のアプローチが試みられています。
線維化の治療薬は、臨床試験を経て市場に出るまでに多くの課題がありますが、成功すれば患者の生活を大きく改善する可能性があります。製薬会社やバイオベンチャーが提供する薬効評価試験サービスを活用し、さらなる研究と開発が進むことを期待しています。