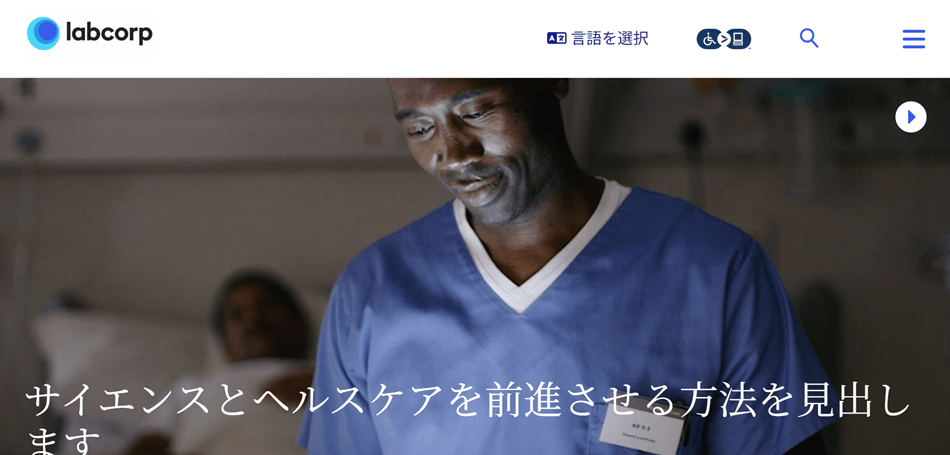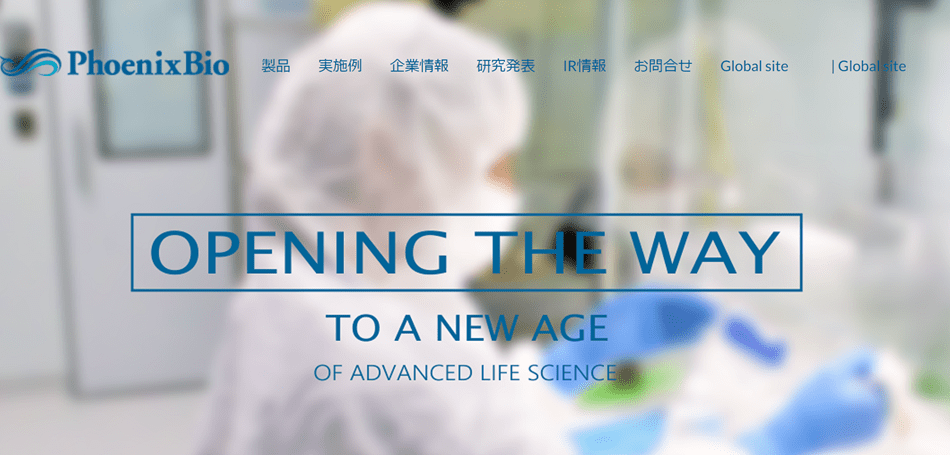新薬リサーチセンター
新薬リサーチセンターは、医薬品の各種薬効の評価について、豊富な経験と実績がある企業です。ここでは、新薬リサーチセンターの非臨床試験の特徴や病態モデル一例、事例などを詳しく紹介します。受託会社を選ぶ際の参考にしてください。
新薬リサーチセンターの非臨床試験の受託サービスの特徴
GLP準拠の高品質な試験
GLP(Good Laboratory Practice)に準拠した非臨床試験を提供しており、信頼性の高いデータを得ることができます。一般毒性試験や生殖発生毒性試験など、多様な試験を用意。医薬品や医療機器の開発過程で必要な安全性評価を厳格に行うことが可能です。
幅広い対応品目と柔軟性
医薬品、医療機器、食品など多岐にわたる分野で非臨床試験を実施しています。特に、皮膚感作試験や細胞毒性試験など、さまざまな種類の安全性試験に対応できる柔軟性が魅力です。多種多様な試験を自社でワンストップ対応しています。
専門的な検査と分析能力
生化学検査から病理組織学的検査まで、専門家による質の高い検査を行っています。信頼性保証部門を設けていることから、高品質なデータの提供が可能です。動物モデルを用いた非臨床試験も行っており、研究者が求める詳細な分析や評価を実現しています。
新薬リサーチセンターが保有する病態モデル一例
病気を治す薬を開発するには、治したい病気を発症した実験動物に対して新薬をテストし、効果のある成分を見つけ出してから臨床試験に臨むのが重要です。
しかし、治したい病気を発症する動物モデルが存在するとは限りません。もしまだ世に無い場合は、場合によっては新規開発してもらう必要もあります。ここでは、同社が保有している動物の病態モデルについて一例をご紹介しています。
生体ストレス可視化マウス(UMAI-Lucマウス)
ルシフェレースをレポーターとして、ストレス応答遺伝子の発現制御において中心的役割を果たすATF4の翻訳誘導を可視化できる、UMAI-Luc遺伝子を持っています。これらストレスの継時的観察を行うツールとして有用です。
小胞体ストレス可視化マウス(ERAI-Lucマウス)
ルシフェレースをレポーターとして、タンパク質合成過程に生じた変性タンパク質の蓄積で引き起こされるストレスである、小胞外ストレスを持っています。細胞を発光で可視化するERAI遺伝子により観察をおこないます。
新薬リサーチセンターの非臨床試験事例
実験的自己免疫性脳脊髄炎(EAE)モデル
マウスに抗原エマルジョンを2箇所に皮下投与し、PTX溶液を腹腔内投与、22~26時間後にさらにPTX溶液を投与することで、多発性硬化症のモデルマウスを作製します。初回PTX投与後、1日1回、媒体または被験物質を経口投与させる実験をおこないました。その結果、アジュバン トともに接種することで、実験的自己免疫性脳脊髄炎(EAE)モデルが誘導された事例です。
ラット及びマウスの脳マイクロダイアリシス
中枢神経系分野では様々な技術・評価システムが必要です。そこで、ラットやマウスの脳マイクロダイアリシスを用いて、自由行動下のマウスから脳内分子を回収し、脳内での神経伝達物質の遊離量測定をおこないました。抗うつ薬・抗不安薬などを投与、神経伝達物質の特定領域内変動を評価したり、特定条件下で目的物質の変動確認をしたりといった活用法があります。
新薬リサーチセンターの企業情報
医薬品や医療機器、化学物質、食品などのさまざまな分野において、各種検査に対応しているCRO企業です。
| 会社所在地
| 東京都千代田区有楽町1-7-1 |
| 電話番号
| 0120-34-0412 |
| 公式サイト
| http://www.ndrcenter.co.jp/ |