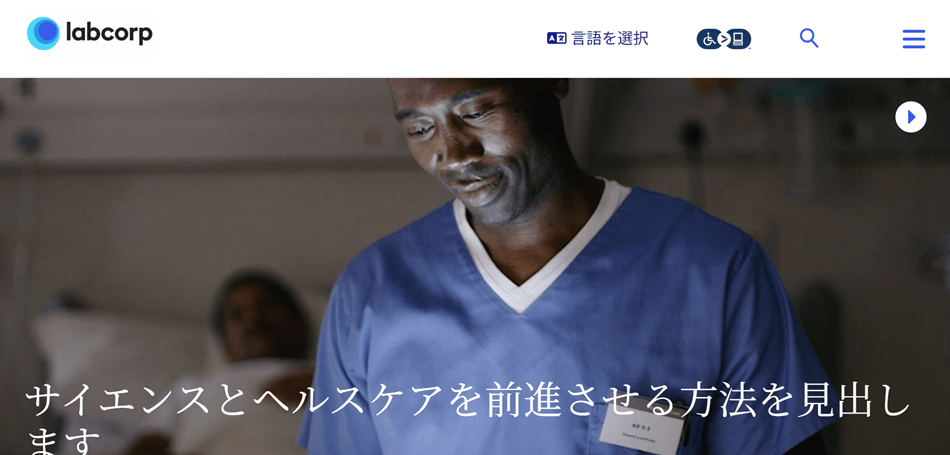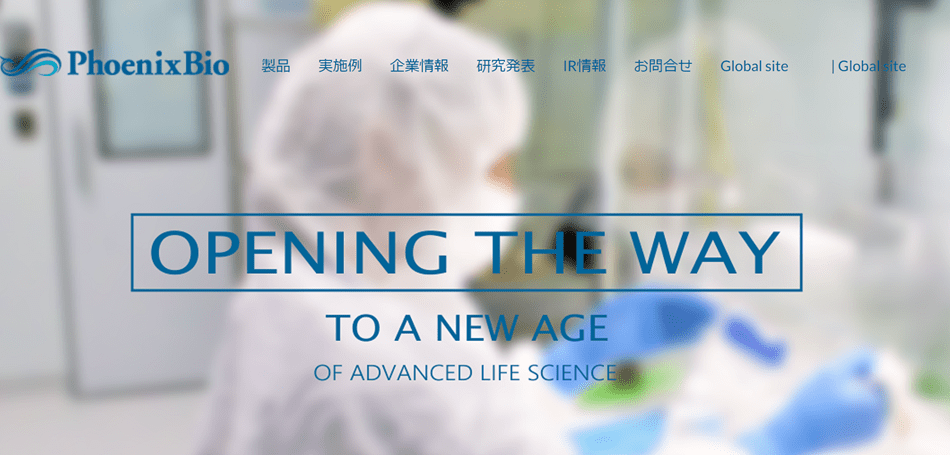新日本科学
新日本科学は、医薬品開発試験の全ステージを受託できる企業グループです。ここでは、新日本科学の非臨床試験の特徴や病態モデル一例、事例などを詳しく紹介します。受託会社を選ぶ際の参考にしてください。
新日本科学の非臨床試験の受託サービスの特徴
豊富な経験と実績
新日本科学は、1957年に設立されて以来、非臨床試験受託の業界でトップシェアを誇ります。医薬品開発における豊富な経験を活かしながら新しい設備を導入していて、製薬企業からは信頼される開発パートナーとして認識されています。特に、新しい医薬品の有効性や安全性評価において高い精度を誇り、迅速にデータを提供します。
自社グループ内のNHP供給体制
実験用の非ヒト霊長類(NHP)の繁殖と供給を自社グループ内で行っています。核酸医薬や遺伝子治療薬など、新しいタイプの医薬品開発に必要な動物モデルを安定的に提供できます。信頼性の高いデータを得ることができ、臨床試験への移行がスムーズになります。
多様な病態モデルの保有
さまざまな病態モデルを用いて非臨床試験を実施しています。特に緑内障や加齢黄斑変性などの眼疾患モデルを開発し、それらを活用した薬効薬理試験に強みがあります。また、「Nose-to-Brain」技術を駆使した経鼻薬物送達システムの開発を進めています。脳疾患モデル研究にも取り組んでいます。
新日本科学が保有する病態モデル一例
病気を治す薬を開発するには、治したい病気を発症した実験動物に対して新薬をテストし、効果のある成分を見つけ出してから臨床試験に臨むのが重要です。
しかし、治したい病気を発症する動物モデルが存在するとは限りません。もしまだ世に無い場合は、場合によっては新規開発してもらう必要もあります。ここでは、同社が保有している動物の病態モデルについて一例をご紹介しています。
サルを使用した緑内障や加齢黄斑変性の病態モデル
新日本科学(SNBL)は、さまざまな病態モデルを用いて非臨床試験を行っています。特に、サルを使用した緑内障や加齢黄斑変性の病態モデルを開発し、それらを用いた薬効薬理試験を受託しています。これにより、製薬企業はこれらの疾患に対する新規治療薬の開発を支援されています。
また、新日本科学は「Nose-to-Brain」技術を活用した経鼻薬物送達システム(N2B-system)を開発し、脳疾患モデルの研究も進めています。この技術により、脳への薬物移行が難しい課題を克服し、新薬開発の可能性を広げています。
新日本科学の非臨床試験事例
具体的な事例として、以下のようなプロジェクトが挙げられます。
眼疾患の非臨床試験
SNBLは、サルを使用した緑内障や加齢黄斑変性モデルを用いた薬効薬理試験を提供しています。これにより、製薬会社はこれらの眼疾患に対する新薬開発を効率的に進めることができています。
経鼻送達技術を用いた中枢神経系疾患の研究
SNBLは、経鼻から脳への薬物送達技術である「Nose-to-Brain」(N2B-system)を活用し、脳への薬物移行性を評価しています。この技術により、脳の血液脳関門を通過しにくい薬物の送達が可能となり、例えばアルツハイマー病やパーキンソン病などの中枢神経系疾患に対する新薬開発に貢献しています。
新日本科学の企業情報
新日本科学(SNBL)は、主に医薬品開発支援を行うCRO(医薬品開発受託機関)として、前臨床試験や薬品分析を提供しています。
また、トランスレーショナルリサーチ事業や、メディポリス事業と呼ばれる医療・健康関連プロジェクトも展開しています。これにより、製薬会社や医療機関をサポートし、医療技術の向上に貢献しています。
| 会社所在地 |
鹿児島県鹿児島市宮之浦町2438 |
| 電話番号 |
099-294-2600 |
| 公式サイト |
https://www.snbl.co.jp/ |