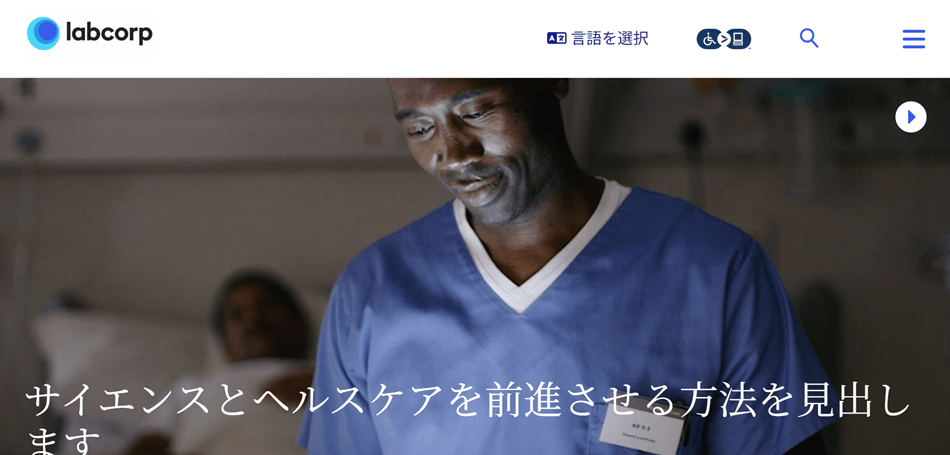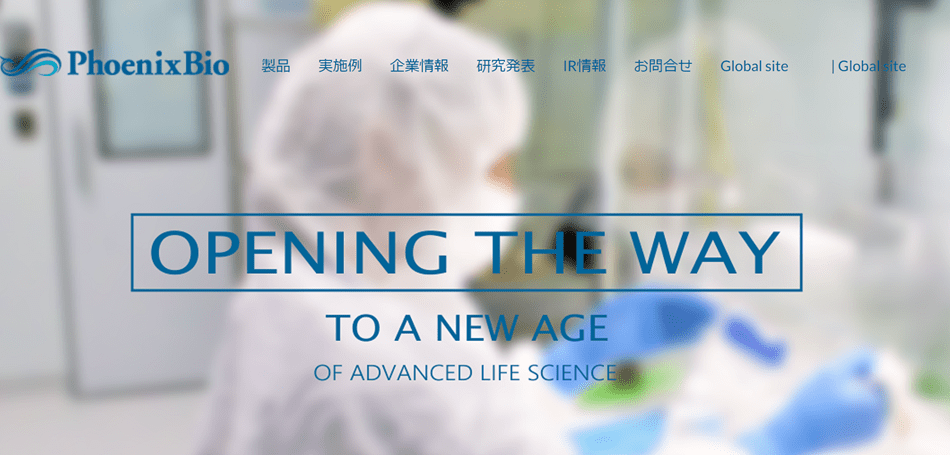免疫疾患の新薬
免疫疾患は、自己の免疫システムが誤って自分の組織を攻撃することで発症する病気です。多くの人々に影響を与えるため、新薬の開発が非常に重要です。新薬開発の過程では、非臨床試験が不可欠です。
非臨床試験は、新薬の有効性を評価するための初期段階の試験で、動物モデルを用いて行われます。この段階での成果が、臨床試験に進むための基礎を築きます。以下では、免疫疾患の新薬開発の事例紹介し、それぞれどのような非臨床試験が使われたかを紹介します。
名古屋市立大学の開発事例
名古屋市立大学では、共同研究により自己免疫疾患を対象とした抗体医薬品候補が開発されました。この抗体医薬品候補は、株式会社ファーマフーズの独自技術「ALAgene® technology」を用いて作製されました。この技術は、ニワトリ由来の抗体を作製するもので、結合力の高い抗体を生産することができます。この新薬は、医薬品医療機器総合機構(PMDA)に新薬臨床試験開始申請が受理されています。
非臨床試験の内容
この新薬開発は公立大学法人横浜市立大学 佐藤 衛名誉教授、山田 道之名誉教授、公立大学法人名古屋市立大学 金澤 智学内講師との共同研究によって開発された、抗体医薬品候補に関して、新薬臨床試験開始申請(IND申請)が受理されました。
慶應義塾大学の開発事例
慶應義塾大学では、関節リウマチの治療に関する研究が行われました。関節リウマチは、免疫システムが関節の軟部組織を攻撃することで炎症を引き起こし、関節を破壊する病気です。リウマチに有効な新薬が何種類も出ているが、どの治療を施しても症状が改善されない患者は10〜20%程度。世界中でリウマチの発症自体を予防することを目指した臨床試験も実施されています。
非臨床試験の内容
研究では、メトトレキサートと生物学的製剤の併用療法が標準治療として推奨されていますが、副作用や金銭的負担を軽減するために、メトトレキサートの用量を減らす臨床試験が行われました。
まとめ
免疫疾患の新薬開発において、非臨床試験は非常に重要な役割を果たします。名古屋市立大学と慶應義塾大学の事例は、それぞれ異なるアプローチで新薬の効果と有効性を検証し、臨床試験への道を開いています。これらの研究は、今後の免疫疾患治療に大きな影響を与えることでしょう。製薬会社やバイオベンチャーが、最新の研究を活用して新薬開発を進めることが期待されます。