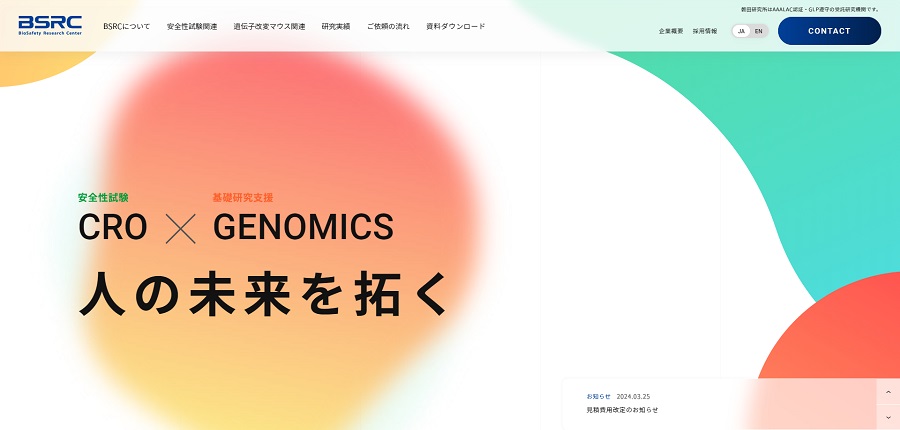非臨床の薬効薬理試験ができる
専門性の高い受託サービスの選び方
10年以上もの時間と莫大なコストがかかる新薬開発ですが、その約75%が臨床試験でドロップ(差し戻し)※されてしまうことをご存知でしょうか?この高いリスクは、前工程の非臨床による薬効・薬理試験に入念な準備の上で取り組むことにより、ある程度緩和させることができます。
そのためには、高い技術力を有する専門性の高い受託会社に依頼するのがベター。ここでは会社選びのポイントと、新薬の対象領域別のおすすめ受託会社をご紹介しています。
【得意領域別】高い専門性を持つ
薬効薬理試験 受託会社5選
ここではeffical編集チームが独自に調査をした受託サービスの中から、多くの病態モデルと試験事例を有する会社を、新薬の対象領域別に分類しました。開発中の新薬に近い領域から、ぜひおすすめの会社情報をチェックしてみてください。
臓器線維化領域の薬効薬理試験なら
「SMCラボラトリーズ」
引用元HP:SMCラボラトリーズ公式サイト
https://www.smccro-lab.com/jp/
こんな人におすすめ
- ・まだ有効成分が見つかっていない疾患の治療薬を開発したい製薬会社
- ・病態モデルすら存在しない領域の創薬にチャレンジしたいベンチャー
SMCラボラトリーズが薬効・薬理試験の
委託におすすめの理由
- 自社開発のSTAM™マウスにより、難度の高い治療薬開発を支援できる
がん領域の治療薬開発ツールとして浸透するSTAM™モデルですが、こと肝臓がんにおいては免疫チェックポイント阻害剤があまり効果を成さないことにより、開発が遅れていると言われています。
そこでSMCラボラトリーズは、がん免疫療法の手法を用い、薬効評価ができる新モデルを開発。これにより、これまで試験が難しかった肝臓領域でも高い精度の評価ができるようになりました。
- 評価できる病態モデルが無い場合、伴走して新規開発してくれる
医薬品を開発するにあたり、ヒトの病態を表現できるモデルは必須。しかしモデルがまだ無い疾病も多く、すでにあったとしても現在の臨床に堪えられない課題を抱えたモデルも多く存在します。
SMCラボラトリーズでは、評価できないモデルの課題を洗い出し、高い技術力で課題を克服した病態を再リリースすることで、この問題を解決。調べても世の中にないなら、ゼロから新規開発も可能です。
SMCラボラトリーズの保有する
病態モデル一例
SMCラボラトリーズでは、独自開発の病態モデル「STAM™マウス」をはじめ、炎症や線維化、代謝、がん免疫などに関連した疾患モデルマウス・25種をラインナップ。
ここではMASH/NASH研究で利用されるSTAM™モデルと、腎線維化モデルとして広く用いられているUUOモデルをご紹介しています。
STAM™ モデル
ヒトMASH/NASH-HCCと同様な病態進行を示すモデルです。後期2型糖尿病を模し、脂肪肝からNASH、線維化、そして肝がんへと病態が進行します。
短期間で病態が進行し、20週齢時で100%肝がんを発症する特徴から、これまでに70件以上の論文で研究内容が公表されています。
片側尿管閉塞(UUO)モデル
腎線維化モデルとして使用されることの多いUUOモデルには、間質性線維症・尿細管萎縮・炎症細胞浸潤などの慢性腎疾患の病理的特徴が認められます。
このモデルは試験期間がたった2週間なので、腎臓の線維化に対する抗線維化薬のin vivoスクリーニング試験に適しています。
SMCラボラトリーズの
薬効・薬理試験 ケーススタディ
世界中で1,000を超えるクライアント※にサービスを提供しているSMCラボラトリーズ。線維化をターゲットとする非臨床試験でのSTAM™マウスの提供を始め、炎症・代謝・がん免疫等の多方面で豊富な実績を誇ります。ここでは薬効薬理試験に無事フェーズ2へと移行した事例をご紹介しています。
SMCラボラトリーズの会社概要
| 会社名 |
SMCラボラトリーズ株式会社 |
| 所在地 |
東京都⼤⽥区南蒲⽥2-16-1 テクノポートカマタセンタービル |
| 電話番号 |
03-6715-9101 |
| 公式サイト |
https://www.smccro-lab.com/jp/ |
網膜神経・眼科領域の薬効薬理試験なら
「薬物安全性試験センター」
引用元HP:薬物安全性試験センター公式サイト
https://www.dstc.jp/
こんな人におすすめ
- ・緑内障、網膜関連の創薬を進めている製薬会社
- ・いち早く有用なデータを手に入れたい創薬ベンチャー
薬物安全性試験センターが
薬効・薬理試験の委託におすすめの理由
薬物安全性試験センターの保有する
病態モデル一例
高眼圧・網膜・ドライアイなどの眼科領域に対する評価を幅広く受託している会社です。イヌ・ウサギ・ラットなど多様な動物で試験ができるので、有用性を見出しやすいのが強みと言えるでしょう。
ウサギキモトリプシン誘発高眼圧モデル
高眼圧状態を継続的に維持できるモデルで、慢性緑内障や眼圧下降薬、緑内障視神経症治療薬、網膜症治療薬などの評価に適用しています。
イヌ乾燥性ドライアイモデル
イヌの角膜に一定量の風を強制的に当てることで、角膜を乾燥させます。乾燥性ドライアイを惹起させることで、角膜上皮障害性ドライアイ治療薬に適用するモデルです。
薬物安全性試験センターの
薬効・薬理試験 ケーススタディ
公式サイトにケーススタディの記載がありませんでした。
薬物安全性試験センターの会社概要
| 会社名 |
株式会社薬物安全性試験センター |
| 所在地 |
東京都新宿区高田馬場1-31-8 |
| 電話番号 |
0493-54-3239 |
| 公式サイト |
https://www.dstc.jp/ |
代謝性疾患領域の薬効薬理試験なら
「ボゾリサーチセンター」
引用元HP:ボゾリサーチセンター公式サイト
https://www.bozo.co.jp/
こんな人におすすめ
- ・高脂肪食負荷・高血圧関連の創薬を進めている製薬会社
- ・毒性病理学等、専門家によるデータを求める創薬ベンチャー
ボゾリサーチセンターが薬効・薬理試験の
委託におすすめの理由
- 生活習慣病の治療薬開発に特化した、応用性のあるデータを得られる
摂餌量や体重、血糖値や脂質パラメーターなどを指標とするin vivo薬効薬理試験、培養細胞を用いたin vitro薬効薬理といったさまざまな試験を実施でき、得意分野である代謝性疾患系の試験を効率よく実施できるのが強みです。
- 毒性病理学等、専門家による信憑性の高い試験を実施できる
ボゾリサーチセンターでは毒性病理学者などの専門家を有しており、豊富な経験と実績から有益なデータ抽出のための試験を行うことができます。いずれも信頼性基準対応試験として実施でき、創薬研究経験者による試験系の提案も可能です。
ボゾリサーチセンターの保有する
病態モデル一例
代謝性疾患領域では、生活習慣病の治療薬を開発するために必要な試験・評価を実施しています。正常動物・疾患モデル動物を用いたin vivo薬効薬理試験が提供メニューの中心です。
高脂肪食負荷肥満モデル
公式サイトにモデル詳細の記載がありませんでした。
卵巣摘出(OVX)肥満モデル
公式サイトにモデル詳細の記載がありませんでした。
ボゾリサーチセンターの
薬効・薬理試験 ケーススタディ
公式サイトにケーススタディの記載がありませんでした。
ボゾリサーチセンターの会社概要
| 会社名 |
B&Iホールディングス株式会社 |
| 所在地 |
東京都新宿区西新宿3-9-12-1201 |
| 電話番号 |
03-5453-8120 |
| 公式サイト |
https://www.bozo.co.jp/ |
神経変性疾患領域の薬効薬理試験なら
「メディフォード」
引用元HP:メディフォード公式サイト
https://www.mediford.com/
こんな人におすすめ
- ・アルツハイマー、うつ病関連の創薬を進めている製薬会社
- ・手術を要する薬効試験が必要な創薬ベンチャー
メディフォードが薬効・薬理試験の
委託におすすめの理由
- 中枢神経作用系の病に対する病態モデルが多く、応用可能性が高い
アルツハイマーやうつ病をはじめ、疼痛・記憶障害・てんかんといった中枢神経系の病気を発症するモデルを多く有しています。うつ病モデルひとつとっても、複数のモデルを保有しているので、細かい病様に合わせた薬効薬理試験が可能です。
- 難度の高い遺伝子改変動物などを使った手術を要する薬効試験ができる
メディフォードはコンベンショナル動物や遺伝子改変動物、ミュータント動物を用いた試験の経験が豊富で、なかでも手術を要する薬効試験を得意とする会社です。PCR、フローサイトメーター、各種細胞を用いたin vitro薬効試験についても知見が多く、有用なデータを得られる可能性があります。
メディフォードの保有する
病態モデル一例
メディフォードでは、薬効薬理試験に使うさまざまな病態モデルを応用した試験を受託しています。新旧を問わず、中枢神経系を中心に、疼痛、感染症、循環器系などのin vitro薬効試験といった幅広い分野の試験を実施しています。
LPS誘発うつ病マウスモデル
リポポリサッカライド(LPS)を投与することでうつ病モデル(マウス)を作製します。強制水泳やテールサスペンションの無動時間を指標として、薬の抗うつ様効果を評価する試験です。
一過性中大脳動脈閉塞(栓子法)モデル
中大脳動脈を閉塞したラットの脳虚血モデル(一過性MCA閉塞)を用い、脳梗塞巣体積・神経症状・ロータロッド試験を指標として薬効を検討します。豊富な経験を持ち、安定したモデル作製が可能です。
メディフォードの
薬効・薬理試験 ケーススタディ
公式サイトにケーススタディの記載がありませんでした。
メディフォードの会社概要
| 会社名 |
メディフォード株式会社 |
| 所在地 |
東京都板橋区清⽔町 36-1 |
| 電話番号 |
03-6905-5860 |
| 公式サイト |
https://www.mediford.com/ |
アトピー性皮膚炎の薬効薬理試験なら
「安評センター」
引用元HP:安評センター公式サイト
https://www.anpyo.co.jp/
こんな人におすすめ
- ・ヒトのアトピー性皮膚炎薬の創薬を進めている製薬会社
- ・ピアレビューされた有用なデータを手に入れたい創薬ベンチャー
安評センターが薬効・薬理試験の委託に
おすすめの理由
安評センターの保有する
病態モデル一例
安評センターではアルツハイマーなど精神疾患系とアトピー性皮膚炎に特化した薬効薬理試験を行っており、特にアトピー性皮膚炎では評価の高いモデルを有しています。
IL33 Tgマウス
このマウスは8週齢以降全てのマウスで、アトピー性皮膚炎を自然発症することが示されています。このモデルを用い、病理組織学的検査、血液生化学検査、ELISA測定、免疫染色、遺伝子解析など、解析を含む非臨床試験受託を提供可能です。
proBDNF KIマウス
尾懸垂試験や強制遊泳試験において、無動化時間が長期化するうつ病様の表現型を示します。うつ病をはじめとする精神・神経疾患に役立てることができます。
安評センターの
薬効・薬理試験 ケーススタディ
公式サイトにケーススタディの記載がありませんでした。
安評センターの会社概要
| 会社名 |
株式会社安評センター |
| 所在地 |
静岡県磐田市塩新田582-2 |
| 電話番号 |
0538-58-1266 |
| 公式サイト |
https://www.anpyo.co.jp/ |
非臨床の薬効・薬理試験受託会社の
選び方のポイント
ここでは会社選びをする前に、新薬開発を取り巻く非臨床の薬効・薬理試験の現状について把握しておきたい方のための情報をまとめました。
臨床での安全性+薬効薬理試験で
約75%も新薬がドロップしてしまう※
冒頭でもお伝えしたとおり新薬が世に出る可能性は低く、安全性試験で50%が、薬効・薬理試験で25%もの新薬がドロップ(差し戻し)されてしまう※という現状があります。
開発から試験のプロセスに10年以上かかることもザラの新薬ですが、膨大なコストをかけて挑むものであることを踏まえると、そのリスクはなるべく回避したいと思うのが本音でしょう。
非臨床の薬効薬理試験に注力すれば
開発期間短縮と通過率向上が見込める
非臨床の薬効薬理試験では、ヒトの病気を模した動物(病態モデル)で効果試験を行います。その際、どれだけ疾患症状がヒトに近いモデルであるかが、有効性を確認するためのカギとなります。適した病態モデルで薬効薬理試験を行い、有効性が認められた後に臨床へと進めば、ヒトへの薬効にも大きく期待できるでしょう。
従来はこのリード特定から非臨床試験、そして臨床試験というプロセスに多くの時間を費やしていましたが、非臨床での薬効薬理試験に注力することで、結果的に臨床試験期間の短縮につながり、コスト削減にも寄与します。
非臨床の薬効・薬理試験は
「専門性」の高い受託会社に依頼しよう
薬効薬理試験は非常に高い専門性を求められることもあり、疾患や対応臓器ごとに特化した技術を持つ受託会社を選ぶのがベター。とはいえ、具体的にどういった基準で専門性の高さを測ればいいのか、判断が難しいのが実情です。
そこでeffical編集チームでは、専門性の高さを表す根拠として「保有する病態モデルの豊富さ」「特許を取得するレベルの技術力」「公開されている事例の多さ」にフォーカスしました。
保有する病態モデルの豊富さ
薬効薬理試験では、薬剤が特定の疾患や状態に対してどのように作用するかを評価します。そのため、試験対象とする疾患に対する適切な病態モデルが必要不可欠です。多くの病態モデルを保有している会社であれば、さまざまな疾患に対して薬剤の効果をテストすることができます。また、特定の疾患に対して独自の病態モデルを開発できる会社であれば、より的確な評価が可能となり、新薬の有効性を高めることができます。
特許を取得するレベルの技術力
非臨床試験は高度な専門知識と技術を必要とする作業です。試験を正確かつ効率的に実施するためには、最先端の技術を駆使できる研究施設や、経験豊富な研究者が在籍していることが必要です。例えば、先進的なイメージング技術やオミックス解析技術を駆使できる会社は、薬剤の効果を多角的に評価でき、より信頼性の高いデータを提供することができます。
公開されている事例の多さ
過去にどのようなプロジェクトに携わってきたか、どの程度の成功実績があるかを確認することで、その会社の信頼性や能力を判断することができます。似たような分野や疾患において豊富な実績を持つ会社は、予測される問題に対して迅速に対応できるノウハウを持っている可能性が高いです。実績が豊富であれば、試験結果の解釈や次のステップへの提案などにおいても信頼できるアドバイスが期待できます。
このサイトでは、この3点を押さえた受託サービスを、
それぞれ得意とする専門領域毎におすすめの会社としてご紹介します。
ぜひ依頼先の検討材料にお使いください。